こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)の久永です。
自社オウンドメディア(狭義の意味である更新性のある記事型メディア)の運用を担当しています。
「オウンドメディア担当に任命されたが、何から手をつければいいのかわからない…」
「立ち上げたはいいものの、更新が続かず成果が出ない…」
ジーピーオンラインでも過去に2度メディアを立ち上げては頓挫した経験があるので、そのお気持ちよくわかります。
多くの企業が大きな期待を込めてメディアを立ち上げますが、その3割は更新が途絶える、いわゆる「休眠状態」に陥っています。なぜ、これほど多くのオウンドメディアは失敗してしまうのでしょうか。
この記事では、オウンドメディア運用が頓挫してしまう根本的な原因を解き明かし、成果を出し続けるための「失敗しないポイント」と、その要となる「運用体制」の作り方を実体験をもとに具体的に解説します。内製と外注の判断基準まで網羅していますので、これから運用を始める方、そして現在の運用に課題を感じている方も、ぜひ最後までご覧ください。
コンテンツ運用の支援もしています
もくじ
オウンドメディア運用はなぜ失敗しやすいのか?
ジーピーオンラインでは現在ご覧いただいている当ブログの前に、2度ナレッジブログの運用が回らなくなり、プロジェクトを頓挫させてしまった経験があります。長く継続させることは、本当に難しいと身をもって実感しました。
多くのメディアが数ヶ月で頓挫する現実
初期の熱意とは裏腹に、日々の業務に追われ、コンテンツ制作の負担は増すばかり。目に見える成果が短期間で出ないことへの焦りから、社内の協力も得られにくくなり、担当者は孤立無援に。気づけば、メディアは放置されてしまうのです。
- 戦略設計の欠如
- 経営層・社内の理解不足
- 属人化とリソース不足
- コンテンツの質と量のジレンマ
- データ・効果測定の形骸化
Zenken株式会社が実施した調査(2022)によると、運営停止中の企業オウンドメディアは全体の27%になり、開始からわずか半年以内で65.5%が更新停止している実態が浮き彫りになっています。運営停止の理由は「運用担当者がいなくなったから」が54.3%で1位になっており、属人化や人的リソースの課題が特に多いと見受けられます。
参考:Zenken株式会社のプレスリリース|2022年オウンドメディアに関する調査
継続できる仕組みと体制づくりができていない
このような状況に陥ってしまう最大の原因は、メンバーの能力やセンスの問題ではなく、組織として「継続できる仕組みと体制づくりができていない」という基盤の課題に尽きます。
オウンドメディア運用は、短距離走ではなく、ゴールの見えにくいマラソンです。開始前に「誰が・何を・どのように・いつまでに」を明確化し、体制とルールを設計することが、継続の前提条件です。
オウンドメディア立ち上げ支援もしています
オウンドメディアの運用に失敗しない6つのポイント

では、具体的にどのような「仕組み」を作れば、オウンドメディア運用は失敗しないのでしょうか。ここでは、運用を始める前に必ず押さえておくべき6つのポイントを解説します。
- メディア運用の目的を明確にする
- KGI、KPIを適切に設定する
- メディア戦略を立て、計画どおりに進める
- メディアをユーザーファーストで設計する
- メディアやコンテンツに独自性をもたせる
- 長期的な運用を視野に入れて計画する
メディア運用の目的を明確にする
まず、「何のためにオウンドメディアをやるのか」という目的を明確に言語化しましょう。
「新規顧客を獲得したい」「ブランドの認知度を高めたい」「採用情報に興味を持つ人材を集めたい」「広告に頼らず集客したい」など、目的によって作るべきコンテンツや目指すべきゴールは大きく変わります。
オウンドメディアでよくある目的は以下の5点です。
- リード獲得・新規顧客獲得
- ブランディング・企業価値の向上
- 既存顧客との関係強化
- 採用力強化
- 広告費削減・マーケティングコスト最適化
引き合い獲得とブランディングなど、目的が複合的になる場合もあります。しかし、そこに求人応募も加えると、大きく属性の異なるターゲットをひとつのメディアに呼び込むことになってしまいます。結果、どちらのターゲットも満足させられないことにもなりかねませんので、目的はオウンドメディアの指針として明確に定めておきましょう。
【関連記事】オウンドメディアとは?意味や種類から目的まで事例を交えて解説
KGI、KPIを適切に設定する
目的が明確になったら、その達成度を測るための具体的な指標を設定します。
まずは最終目標となるKGI(Key Goal Indicatorの略で「重要目標達成指標」と訳される指標)を決め、それに付随するKPI(Key Performance Indicatorsの略で「重要業績評価指標」と訳される中期的な指標)を立てます。
| KGI (Key Goal Indicator) |
最終目標を定量的に示す指標(例:オウンドメディア経由の月間お問い合わせ数10件) |
|---|---|
| KPI (Key Performance Indicator) |
KGI達成のための中間指標(例:Googleアナリティクスでの月間アクセス数10,000、記事からの資料請求数50件) |
これらの指標があることで、チームは常にゴールを意識でき、施策の評価や改善も的確におこなえるようになります。指標に対する具体的な数値は、過去の転換率などを参考に算出するか、自社に例がない場合は仮で数値を設けて施策を打つ中で検証・修正をおこなうとよいでしょう。
【関連記事】KPIとは?意味と設定方法、KGIとの違いを解説
メディア戦略を立て、計画どおりに進める
目的とKPIが決まったら、それを達成するためのメディア戦略と具体的な実行プランに落とし込みます。
「誰に(ターゲット)」「何を(コンテンツ)」「どのように(SNSでの拡散も含む発信手法)」を定義し、いつまでに何本の記事を公開するのか、といったスケジュールを立てましょう。計画があることで、進捗管理が容易になり、場当たり的な運用を防ぐことができます。
また、担当者や執筆者などもあらかじめ決めておきます。「空いた時間に書きたい人が書く」ルールで定期的に更新していくのは、基本的には不可能と考えておくほうがよいかと思います。論理的に組み立てて、計画通りに進めることを心がけましょう。
メディアをユーザーファーストで設計する
運用で忘れがちなのが、「読者にとって有益な価値があるか」の視点です。
企業が伝えたいことだけを発信するメディアは、誰にも読んでもらえません。読者が抱える悩みや課題は何か、どんな情報を求めているのかを徹底的に考え、その解答となるコンテンツを提供すること(=ユーザーファースト)が、メディアが支持されるための大前提です。
そのため、十分な情報を得ることができない記事内容や、自社製品の購入を勧めるポップアップが何度も出てくるサイト仕様など、検索行動を阻害する設計はユーザー離れの原因となってしまいます。オウンドメディアを立ち上げる際には常にユーザーファーストを意識しましょう。ユーザーファーストのメディアづくりは検索エンジンで上位表示されるための必要条件です。
メディアやコンテンツに独自性をもたせる
競合他社も同じようにオウンドメディアを運営している中で、読者に選んでもらうためには「独自性」が不可欠です。自社の専門知識、独自の成功事例、お客さまの声、社員のインタビューなど、他社には真似できない切り口で情報を発信し、「このメディアでしか得られない価値」を提供しましょう。
類似のオウンドメディアがすでにある場合、どれだけ独自性を出して差別化できるかがポイントになってきます。新しい切り口で展開することや、自社のノウハウを公開していくことを検討してみてください。競合には出せない情報を掲載することができれば、そのままユーザーが訪れる理由になってくれます。
長期的な運用を視野に入れて計画する
オウンドメディアは、リスティング広告のようにすぐ成果が出るものではありません。
長期的な運用が実現してこそ、オウンドメディアは効果を発揮します。1年後、2年後、どんなメディアに成長させて、どんなコンテンツを拡充していくのかも想定しておきましょう。
例えば、運用開始初期はまずは記事数を増やすことの優先度を挙げ、クオリティにこだわり過ぎずに定期的な更新を目指し、ある程度コンテンツが溜まったところで、成果の出ていないものやクオリティの低いもののブラッシュアップに入ります。SEOの観点では、まずは検索ボリュームが少なく狙いやすい記事を作りつつ、将来的にはビッグワードでも上位表示できるように同じテーマでまとめていくことを視野に入れて運用していきます。
先のビジョンが見えていると、余計な不安を抱えることがなく、チーム一体となって同じ方向を向いていけるかと思います。短期間での成果を求めすぎず、中長期的な視点で腰を据えて取り組んでいく認識を、経営層も含めて社内全体で共有することが非常に大切です。
継続の鍵を握るのは運用体制づくり
失敗しない6つのポイントを押さえた上で、オウンドメディアを継続させる最も重要な要素が「運用体制」です。ここからは、オウンドメディアの体制づくりについて解説していきます。
なぜ専門の体制が不可欠なのか?3つの理由
運用が成功するかどうかは、体制づくりができるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。その理由は主に以下の3点です。
- コンテンツ制作には膨大な時間や労力がかかるため
- 多岐に渡る業務それぞれに専門知識が要るため
- 高品質なコンテンツを作りやすいため
コンテンツ制作には膨大な時間や労力がかかるため
オウンドメディア運営の業務を、ざっくり6つに分解してみましょう。
- キーワード戦略・調査
- コンテンツ企画・骨子作成
- コンテンツ作成(ライティング)
- 原稿の校正・添削
- コンテンツ公開作業
- 効果計測・改善提案
こうして洗い出してみると、想像以上にやるべきことがあるのに気がつくのではないでしょうか。
オウンドメディアは社内リソースの都合上、専任を立てずに兼任する形で運営されることが多いです。しかし、実際は膨大な業務をおこなう必要があり、本気で取り組むのであればとても片手間でできるような業務量ではありません。オウンドメディアを立ち上げてもすぐに更新が滞ってしまう原因はこうしたところにもあります。
「オウンドメディアは広告費よりも安く済む」というイメージがついていますが、タスク量は決して少なくありません。これらを継続してやり遂げられるだけの人員確保と役割分担は必須と言えます。
多岐に渡る業務それぞれに専門知識が要るため
オウンドメディア運用には、SEO、ライティング、編集、デザイン、Webサイト制作、アクセス解析など、多岐にわたる専門知識が求められます。特に「キーワード戦略・調査」、「コンテンツ作成(ライティング)」、「効果計測・改善提案」などは得意不得意が大きく分かれ、かつこのすべてに秀でている人材がいるとは限りません。
ひとりの担当者が全ての専門知識を持つことは困難であり、それぞれの専門性を持った人材がチームを組むことで、初めてメディアの品質は担保されます。
高品質なコンテンツを作りやすいため
専門チームによる分業制は、各担当者が自身の得意分野に集中できるため、コンテンツ全体の品質向上につながります。
編集者による客観的な視点でのチェックや、複数人でのアイデア出しなど、チームで取り組むことで、より読者にとって価値の高いコンテンツを生み出すことができるのです。部署を越えて連携することになるので、あらかじめ関係する部署を巻き込んだ体制にしておくとスムーズです。メディアに対する社内の理解が深まれば、運営もよりしやすくなるので、できるだけ関連部署には参加してもらうようにしましょう。
体制づくりでまずやるべきこと5つ
オウンドメディア運営の体制づくりでやるべきことは主に5つです。
- オウンドメディア運営の部署設立
- 十分な人材と予算の確保
- 運営に関する認識の共有
- クオリティチェックの仕組み化
- 標準化・効率化のツール導入
オウンドメディア運営の部署設立
先述のとおり、オウンドメディア運用は片手間で成功するものではありません。可能であれば、まずは専門の部署やチームを正式に立ち上げましょう。専門部署として確立することで、担当者のリソースをオウンドメディア運営に充てやすくなります。また、専門部署があることで、他部署からもオウンドメディア運営の重要性や負荷の大きさを認識してもらえることも期待できます。
十分な人材と予算の確保
専門部署を設立したら、次に必要な人材と予算を確保します。
人材の確保においては、全てのメンバーが専門部署に所属できなくても問題ありません。他部署の専門家に協力を依頼する場合は、「どのような役割で、月に何時間程度関わってほしいのか」を事前に明確にし、関係部署の上長も含めて合意形成しておくことが円滑な連携の鍵です。
予算の確保においては、外部パートナーへの委託費や有料ツールの利用料はもちろん、社内リソースの人件費もコストとして意識することが重要です。ライティングなどの工数を把握し、費用対効果を常に検証する癖をつけましょう。
運営に関する認識の共有
運営の方針や打ち出すメッセージに共通認識がないと、担当した人によって記事の方向性がばらばらになってしまいます。関係者には目的やKGI、KPI、ターゲットのペルソナ像、カスタマージャーニーやロードマップなどの情報は漏れなく共有するようにしましょう。
また、社内全体としても、できるだけ理解を促しておくのが理想です。自社にとってオウンドメディア運営がどれくらい大事なプロジェクトか、将来的にどのようなメディアに育てていくつもりかなど、ビジョンを周知していきましょう。
クオリティチェックの仕組み化
メディアの信頼性を担保するため、公開前の品質チェックは欠かせません。誰が、どのような基準でチェックするのか、明確なフローを確立しましょう。チェックすべき項目は、主に以下の3つの視点があります。
| 信頼性に関わるチェック | 内容の事実確認、著作権や薬機法などのコンプライアンス遵守、他メディアからの盗用がないか |
|---|---|
| 専門性・ブランドに関わるチェック | 企業としての見解と相違ないか、ブランドイメージを損なわないか、専門家としてふさわしい品質か |
| 基本的な品質チェック | 誤字脱字、表記ゆれ、読みやすさ(改行・段落)、リンク切れなど |
標準化・効率化のツール導入
運用の属人化を防ぎ、担当者が本来注力すべき創造的な業務(戦略立案やコンテンツ企画など)に時間を使うために、ツールの導入による業務の標準化・効率化は不可欠です。
ジーピーオンラインでも複数人でメディア運用する体制づくりにあたって、まず検討したのが品質の標準化に貢献するツール導入です。具体的には以下のツール・サービスを導入しました。
- プロジェクト管理ツールのBacklog(バックログ)
- SEOツールのPascal(パスカル)
- 校正ツールの文賢(ブンケン)
- 原稿作成はGoogleドキュメント
- CMSは独自カスタマイズしたWOW(ワウ)
これらのツールを組み合わせることで、マニュアル化された業務フローを支え、品質の均一性を保ちながら効率的な運用体制を構築できます。企業規模やオウンドメディアの特性によって最適なツールは違うため、自分たちにあったツール導入を検討してみてください。
【関連記事】オウンドメディア運用に便利なChrome拡張機能おすすめ15選
内製(インハウス)と外部委託(アウトソース)の判断基準
運用体制を検討する上で、必ず直面するのが「自社でやるか(内製)、外注するか」という問題です。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に合った手段を選ぶことが大切です。
内製のメリット・デメリット
社内リソースで運用する「内製」のメリット・デメリットです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
外部委託のメリット・デメリット
外部パートナーへ依頼する「外部委託」のメリット・デメリットです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
どこまで任せる?外部委託の依頼範囲3パターン
外部パートナーに委託する際の依頼範囲は大きく3つに分かれます。
パターン1.企画から執筆まで一括委託
キーワードの選定から構成案の作成、執筆まで一括で外部パートナーが請け負うやり方です。社内のオウンドメディア担当者は確認作業だけをおこなうので、負担が軽く、専任が付けられない場合でもオウンドメディアを運営していくことが可能となります。
社内にリソースやノウハウが全くないケースに効果的ですが、企画からすべて委託することになるので費用は高額になりがちです。自社で人材を確保し、ノウハウを蓄積しながら運営するのとどちらが費用対効果を高くできるかを比較して決めるのがおすすめです。
パターン2.コンテンツ制作のみ委託
戦略の設計や企画は自社でおこない、コンテンツ制作の実務部分だけ委託できます。
大まかなテーマのみ渡せば、おすすめのキーワード選定から請け負ってくれる業者もあれば、選定したキーワードを渡せば構成案から作成してくれる業者もあります。ライティングを自社でする必要がなくなるので、その分、企業担当者は運用の要となる企画フェーズに時間を最大限使うことができます。
パターン3.運用支援・コンサルティング委託
オウンドメディアが軌道に乗るまで支援してくれるサービスもあります。
サービスの詳細は業者によってさまざまですが、SEO対策の基本やライティングのコツをセミナー形式で教えてくれたり、戦略の練り直しや施策実行のサポートをしてくれたりします。単純に企画や制作だけを外部委託する時と違い、最終的にはインハウス化を目指すので、社内に知見が溜まっていく点がメリットです。
外部委託を検討する際に決めておくべきポイント
外部パートナーとの連携を成功させ、期待通りの成果を得るためには、事前の準備と明確な合意形成が不可欠です。委託を開始する前に、少なくとも以下2つのポイントは具体的に決めておきましょう。
役割と責任範囲(R&R)の明確化
「どこからどこまでを自社が担当し、どこからを委託するのか」の役割分担と、それぞれの責任範囲(R&R:Role and Responsibility)を明確に定義しましょう。ここが曖昧なままだと、「言った・言わない」のトラブルや、業務の抜け漏れが発生する原因となります。
具体的には、コンテンツ制作の各工程(戦略立案、キーワード選定、構成案作成、執筆、校正、入稿など)ごとに、どちらが主担当で、どちらが確認者なのかを一覧表などで可視化しておくことをおすすめします。
品質の基準となるレギュレーションの共有
外部パートナーが貴社のブランドイメージや読者層に合った高品質なコンテンツを制作するためには、明確な指針が必要です。メディアの目的やペルソナ像を共有すると同時に、以下のようなレギュレーションを資料として用意し、共有しましょう。
- ターゲット読者(ペルソナ)の詳細
- 文章のトーン&マナー(例:専門的で信頼感のある文体、親しみやすく語りかける文体など)
- 表記統一ルール(例:漢字とひらがなの使い分け、専門用語の定義など)
- コンプライアンスに関する注意事項(例:使用NGな表現、引用・参照のルールなど)
これらのレギュレーションがあることで、成果物のクオリティが安定し、手戻りや修正の工数を大幅に削減できます。
まとめ:盤石な運用体制でメディアを成功に導こう
オウンドメディアの成否を分けるのは、運用開始時の熱量ではなく、持続可能な運用体制を構築し、地道な改善を継続できるかどうかにかかっています。
成功するためには片手間でやる意識を捨て、体制づくりと予算面を固めて、長期戦であることを前提に戦略的に進めていきましょう。
- 失敗しないポイントを押さえ、長期的な視点で計画する
- 自社に合った運用体制を構築し、チームで取り組む
- 必要に応じて外部の専門家の力も借りる
これらの要点を押さえ、盤石な運用体制を築くことが、オウンドメディア成功への最も確実な一歩です。この記事が、貴社のメディア運用を成功に導くための一助となれば幸いです。
オウンドメディアの運用ならおまかせ
ジーピーオンラインのコミュニケーションデザインサービス
ジーピーオンラインでは、Webサイト制作サービスだけでなく、企業のコミュニケーション戦略を総合的に支援する「コミュニケーションデザインサービス」もおこなっています。
近年、企業を取り巻くコミュニケーション環境は急速に変化しており、従来の広報活動だけでは効果的な情報発信が難しくなっています。オウンドメディアを基軸に一貫性のあるメッセージ発信と適切なチャネル選択が重要です。
コミュニケーションデザインサービスでは、お客さまの課題解決に必要なコミュニケーション施策を立案し、分析・企画からコンテンツ制作・媒体運用までトータルワークでご提供します。戦略設計から実行支援まで一貫したサポートを提供し、企業の価値向上と持続的な成長を支援します。
最適なコミュニケーションデザインへ!
会社案内・サービス資料をダウンロード
当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。
▼資料内容(一部)
-会社紹介
-事業紹介
-サービス紹介
-強みとこだわり
-多様な制作実績
-プロジェクトの進め方
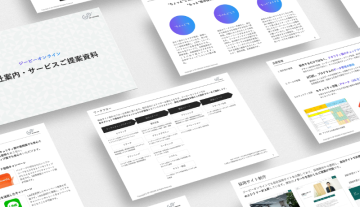
WRITER久永愛子 Webマーケーター
2000年在学中から独学でWebサイト制作を経験したのち、2007年にジーピーオンライン入社。ディレクター、総務、広報、人事・採用などさまざまなポジションでの経験を活かし、Webサイト運用やWebマーケティングに関する情報を分かりやすく発信していきます。


